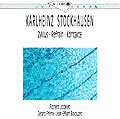|
|
MICHAEL TILSON THOMAS RALPH GRIERSON
ROGER KELLAWAY STEVE REICH TONY RANEY
Recording 1972, 1973 / Angel Records
あー、もしかするとショップで大声を出したかもしれない。しかも「ワオ!」って言うつもりがどう間違ったか出てきた言葉が「チャオ!」。でもまあ店内ではワーグナーだかヴェルディだかのオペラがガンガンかかっていたのでたいして目立たなかったようだけど。
というのもこのCD。すごい!の一言。なんていったってマイケル・ティルソン・トーマスとスティーヴ・ライヒの共演。曲はもちろんライヒ作品で、『4台のオルガン:4台のエレクトリック・オルガンとマラカスのための 』。作曲者とMTT、それにラルフ・グリアソンとロジャー・ケラウェイ、トム・レイニー加わっている。他に、ストラヴィンスキーの『春の祭典』(2台ピアノ版)とジョン・ケージの『3つのダンス』(2つのプリペアードピアノのための)がカップリング。
この楽曲とメンツ(プレイヤー)。なにか熱いものを感じさせずにはおかない組み合わせだ。
『春の祭典』は僕のもっとも好きな曲のひとつ。もちろんオーケストラ版のほうが断然好きだけど、このピアノ版もなかなか良い。たしかこのヴァージョンの初演はストラヴィンスキーとドビュッシーというこれまたすごいメンツ。
ただピアノ版に関しては、少し前にファジル・サイの多重録音のやつを聴いてしまったからなあ。あの衝撃の後だからどうしてもちょっと穏当な印象になってしまう。
ケージの『3つのダンス』はすごく良かった。ほんとうにスリリング。ほんとうにエキサイティング。ほんとうにファンタスティック。血騒ぎ肉踊るというのはこういうことを言うんだろうと改めて思う。
これがピアノの音だとは到底思えない(そう、プリペアードされたピアノの)奇妙な音の粒がまるで原子運動のように規則的なんだか不規則的なんだか、要するにその運動のパターンが掴みきれないままに、とにかく、じゃらじゃらとスピーディーに流れ落ちていく……のを見ているようだ(見ているしかない)。
うーん、音楽の聴き方がまた一つ変わったようだ。まさしく HAPPY NEW EARS!
そして『4台のオルガン』。 まあいつものライヒである。単純なフレーズが繰り返し繰り返し流れるミニマル・ミュージック。こういった曲は好き嫌いがあると思うけど、僕はわりと気に入っている。
録音も最新の技術と比べると決して良くはないのだけれども、でも、この「音」ってなんか70年代の熱い息吹のような、なんか当時の若いミュージシャンたちの時代精神ようなものを感じさせてくれる。
このジャケットもそう。ちゃちい電子オルガン(音もちょっとちゃちい)にマラカスを持った若者たち。彼らの表情から服装から(ヘンな長髪)、あるいは眼差しに至るまで時代の刻印を感じてしまう。そうだ、ライヒの最初の活動はアメリカ西海岸であった。彼はそこで自由な空気に触れた。公民権運動を支持する劇団の音楽も担当した。彼の音楽は、シュトックハウゼンやブーレーズらのいるヨーロッパとは違ったやり方で音楽を(そして世界さえも)革新しようとした。
そういえば、ちょうどこのCDの録音時期は、帝王として音楽界に君臨していたヘルベルト・フォン・カラヤンが二度目のベートーヴェン交響曲全集を行っていたころだ。カラヤンの絶頂期でありまた彼がマーラーやシェーンベルクあたりにも手を出していたころである。超一流オーケストラを手中にし、これ以上ないゴージャスな響きで傑作中の傑作であると認められた古典音楽を振る巨匠指揮者。その一方で、新進作曲家の新曲を電子オルガンとマラカスでもってプレイする若手ミュージシャンたち。
なんかこの構図って、いかにもって言う感じで、ちょっと微笑ましい。
[ANGEL RECORDS ]
http://www.angelrecords.com/