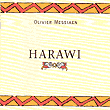|
ミのための詩 7つの俳諧
|
フランソワーズ・ポレ(Sp)
ピエール・ローラン・エマール、ジョエラ・ジョーンズ(P)
クリーヴランド管弦楽団
指揮 ピエール・ブーレーズ
recording 1994,96 / DG
『ミのための歌』はメシアンの最初の妻、ヴァイオリニストであったルイーズ・ジャスティン・デルボワとの「聖なる結婚」を記念して作曲された。ピアノ版とオーケストラ版があり、このCDはオーケストラ版。メシアンの初期の作品であるため、前衛音楽というよりは、濃厚なロマンを漂わせた、まるでワーグナーにような音楽になっている。ドラマティックで激しい感情表現を聴かせる。オーケストラも多彩に変化し、メシアンならではの官能的な響きを感じ取れる。
メシアンの二人目の妻は、ご存知イヴォンヌ・ロリオ。世界的なピアニストであり『幼子イエスの20のまなざし』の初演者でもある。そのメシアンとロリオが「ハネムーン」に訪れたのが日本。そこでメシアンは、日本の印象を綴り(音楽化し)、『7つの俳諧』を作曲した。
こちらはいつものメシアン。どぎついまでの音色が飛び交い、凝ったリズムが時間感覚を麻痺させ、トレードマークの鳥の声が賑々しく舞う。
ただ、『宮島と海中の鳥居』はどうしてこれが宮島なんだろうか……。なんだか分子の運動のような、あるいはパチンコ店の「チン、ジャラジャラ」という雑音の中で、渋い民謡が慎ましく流れているような──そんな音楽に聞えるけど……(しかし、まあ、ロラン・バルト先生のように、パチンコを独特の美学として捉えた人もいるので、これも日本の神秘を独特の感性で表現したものかもしれない)。
それでも『雅楽』なんかは妖しいくらい美しい。いうまでもなくこの曲は、日本の雅楽をオーケストラで「再現」したものであるが、篳篥をトランペットと2つのコールアングレに、笙を8つのヴァイオリンで「表現」(真似る)するなど、さすがは「音の分析」に長けているメシアンだ。もともとの──西洋音楽からすれば──非和音的な「音塊」が、実に前衛音楽の響きを獲得している。あのドヨーンとしたリズムもだ。
ううむ、「洋才」恐るべし。「普遍」を標榜する西洋文明(あるいはメシアンが帰依しているカトリック)の前では「独自文化」なんてものは風前の灯火なのかもしれない……なんてね。