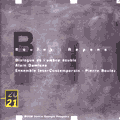|
|
アレクサンダー・バラネスク(第1ヴァイオリン、ビオラ)
クレア・コナーズ(第2ヴァイオリン)
ニック・ホランド(チェロ)
CONSIPIO RECORDS
『ポゼスト/POSSESSED』ではクラフト・ワーク、トーキング・ヘッズを取り上げたバラネスク・カルテットだが、この『East meets East』ではYMOをカヴァーしている。
YMOといえばなんといっても「電気系」(テクノ)のバンドだろう。それが弦楽四重奏という西欧音楽の中核とも言える、まったくコンサーバティブなスタイルで演奏されるとは。
しかしさすがはバラネスク・カルテット。弦楽四重奏の機能美を存分に証明する演奏だ。そこには弦楽四重奏ならではのアレンジが施され、取って付けたような違和感はまったくない。高橋幸宏が監修をしていることにより、オリジナルとの齟齬も解消されているはずだ。
なによりこのバラネスクの演奏を聴くと、すごく気分が昂揚する。聞こえてくる音楽は素晴らしくスタイリッシュで抜群にノリが良い。
ああ、「TECHNOPOLIS」ってこんなにかっこいい曲だったんだ、「BEHIND THE MASK」はハーモニーが絶品。「RYDEEN」は、断片的な素材が次第に型を形成していき、やがてあの有名なメロディーになっていくところなんてゾクゾクくる。
ただし、その時点でYMOという存在を忘れている。そのエレクトロニック・サウンドは、かつてどこかで聴いた思い出の中のエコーになる。代わって、今、思い浮かべるのはベートーヴェンであり、シューマンでありバルトークである。
そしてバルトークから<東>を感じさせるように、この音楽も、時折、<東>を感じさせる。
それでもこのアルバムのタイトルは『East Meets East』である。『West Meets East』にはならない。
バラネスク・カルテットは、ルーマニア出身のアレクサンダー・バラネスクにより1987年ロンドンで結成された。まだ<東>が存在していた。しかしそれだけで<東/East>を強調したわけでもないだろう。<西/West>には、時に「優越」という意味があるにしても。
彼らは、音楽を含む様々な自分たちの「角度」と「方向」に誠実なだけだと思う。
(一方で、先日読んだ高城響の<心無い>「やおい」論のように、自分の「角度」からみて、必死に「優越」したいという「願望」からくる「強情さ」しかないものも、この世界には流通している)
ジャンルの壁を容易くぶち破り、風穴を開け、越境するバラネスク。彼らはサウンドを豹変させ、既存のコードを覆す。そこから新鮮な音楽が発ち現われる。